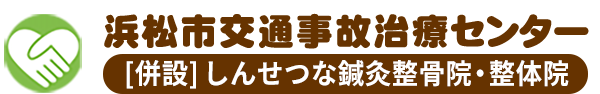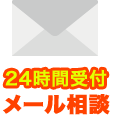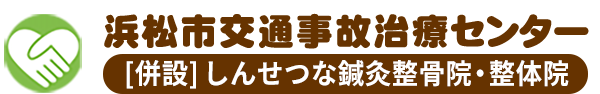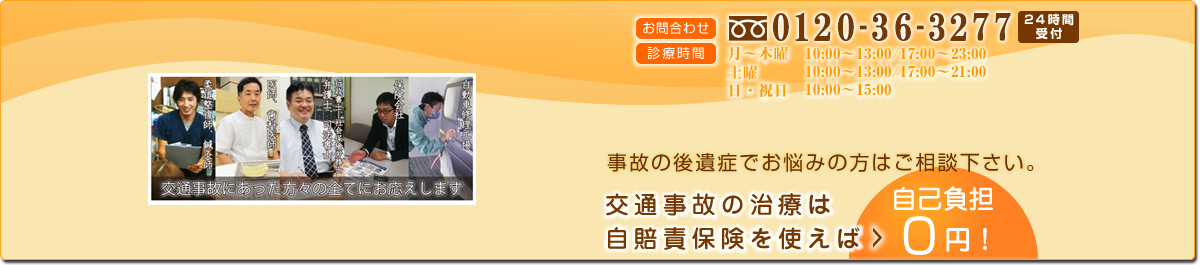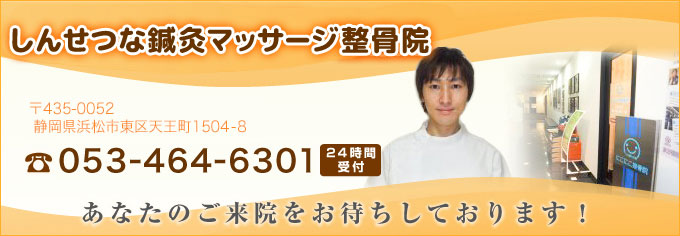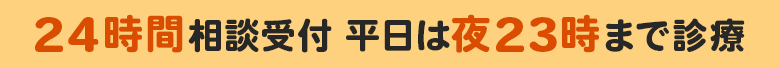示談交渉に臨む際の注意点・必要書類
こんにちは、交通事故専門士の石田です。
前回は、「示談」の基本で、示談とはどのようなものかをお話しいたしました。
今回は、実際に示談交渉に臨む際の注意点・必要書類をお伝えします!

交通事故の示談交渉で注意すべきこと
示談書を作成し、交通事故施術終了後の示談が成立してしまうと、その後に示談交渉の際と異なる事実が発覚しても、示談をやり直すことは原則できなくなってしまいます。そこで、被害者が交通事故についてある程度の法律知識を身につけることが必要になってきます。
加害者側の保険会社の担当者の話をそのままうのみにしてしまうと、病院や整形外科の施術ひ等の損害賠償が受け取れるはずの分より減ってしまったり、病院や整形外科の施術費を払ってもらえなかったりすることになりかねないのです。軽い怪我であればまだいいのですが、後遺障害の残るような大きな事故であった場合、一生後悔し続けることになってしまいます。
交通事故の示談交渉で後悔しないための注意ポイント
・示談交渉をした年月日、できるだけ詳しく話し合いの内容をメモ!
・ボイスレコーダーで会話を録音!
・平常心を保つ! 冷静に言いたいことをはっきりと担当者に伝えよう。
・保険会社から「これ以上は出せません」と言われても、それは保険会社の内部基準! 本当はどうなのか、弁護士などに相談し検討してみましょう。
・どうしても納得できない場合は、示談に応じる必要はない!
(ただ、訴訟を提起することになります)
意外と難しく、重要になるのが平常心。
常に平常心を保つように心がけ示談交渉に臨むことで、納得のできる示談をしましょう。
交通事故の損害賠償の示談交渉に必要な書類
① 交通事故証明書
いつ、どこで、どのような事故が発生したかを証明する書類です。自動車安全運転センターへ請求します。
②交通事故の 診断書と受付報酬請求書
診断書・・・障害の内容を記載してある書面。
受付報酬請求書・・・施術内容の明細書。病院、整形外科の入院日数、入院費、どのような薬を投薬したか、どのような注射をしたか、入院費、施術費などが細かく書かれています。
どちらも交通事故施術を受けた病院や整形外科へ有料で請求できます。
③ 領収書
入院費、施術費、付添人費用、入院諸雑費(交通費、通信費、日用雑貨品費、栄養補給費)などの領収書は捨てずにすべてきちんと取っておきましょう。
④ 収入の証明書
給与明細書もしくは源泉徴収票。自営業の方は、確定申告書の写しまたは納税証明書。その他、被害者の収入が証明できるもの(会計帳簿など)
死亡事故の場合
交通事故被害者の相続人が損害賠償の請求をすることができます。
- 死亡した被害者の除籍謄本
- 相続人本人の戸籍謄本
- ・②は被害者の相続人であるという証明の為必要になります)
- 死体検案書・受付報酬明細書
- 領収書
さらに、死亡事故であった場合、亡くなった方の葬儀費用や墓碑建立費、仏壇の購入費などの明細や領収書もとっておきましょう。損害として認められる可能性があります。
今回は、交通事故後の示談交渉の注意点についてお話しさせて頂きました。事前の心構え、用意するものなど、お分かり頂けましたでしょうか。ご不明なことがございましたら、いつでもお声かけくださいね。
次回は、交通事故の相談機関について詳しくお伝えいたします。
にほんブログ村 人気ブログランキングへ